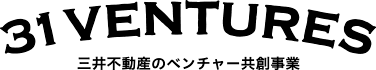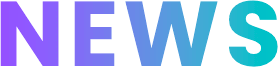 お知らせ
お知らせ
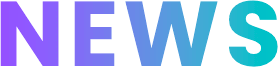
CVCは何を目指す?不動産テックの現在地は?「SusHi Tech Tokyo 2024」で届けたリアルな声

三井不動産 ベンチャー共創事業部がゴールドパートナーとして出展した「SusHi Tech Tokyo 2024(東京ビッグサイトにて5月15日(水)、16日(木)に開催)」の「グローバルスタートアッププログラム」。当日は、出資先のスタートアップやVCなどのステークホルダーと、ベンチャー共創事業部のメンバーによるパネルセッションも用意しました。
2日間で、全15回のセッションを実施した今回。本記事では2日目に開催された3つのセッションをピックアップし、その内容をご紹介。今回のパネル展示にご協力いただいた2社の出資先企業の声もお届けします。
※出展の裏側や今後の展望を掲載した第一回記事はコチラ
CVCは何を目指すか。M&Aを視野に、ファイナンシャルリターンから目を逸らしてはいけない
今回お届けする1つ目のセッション内容は「大企業オープンイノベーションぶっちゃけトーク」。ベンチャーキャピタルの経営経験も長く、事業会社のオープンイノベーションについて書いた『企業進化を加速する「ポリネーター」の行動原則 スタートアップ×伝統企業』の共著者でもある中垣 徹二郎氏に、オープンイノベーションに関する様々なことを赤裸々に語っていただきました。
最初のテーマは「スタートアップへ出資する意義ってなんですか?」。改めてスタートアップへ出資する意義について、中垣氏は次のように話します。

中垣氏「ライバル会社に先んじて買収するチャンスを得る、また、新しい市場に入るタイミングでスタートアップの協力を得られることですね。私としては、CVC活動においては将来的な買収を選択肢として持つべきだと考えています。アメリカのCVCはM&Aを目的に、出資を行うケースも多くあります。とはいえ、日本の場合、スタートアップの買収に慣れている会社はあまりないため、まずはオープンイノベーションで協業することが初めの一歩だと思いますが、最終的にM&Aを目指してもよいのではないでしょうか。スタートアップの買収において気を付けなければならないのは、買収先をコントロールしようとするのではなく、買収先のビジネスがどのようにしたら立ち上がりやすいか、そこに勤めている従業員の方々がいかに働きやすくなるか、どういうサポートができるのか、を一番に考えることです」
続いての話題は、出資にあたって事業シナジーなどを生み出す「ストラテジックリターン」と、金銭的なリターンである「ファイナンシャルリターン」のどちらを目指すべきなのか。中垣氏は永遠のテーマだと話しつつも、ファイナンシャルリターンを意識すべきだと言います。
中垣氏「結局、ファイナンシャルリターンを得られなければCVCの機能も継続できません。またファイナンシャルリターンを期待できない投資先はクオリティが高くないスタートアップである確率も高い。さらに、協議しながら事業上のシナジーを生んでいくにしても、出資先企業単独である程度の利益を上げられるだけの規模感が必要です。ファイナンシャルリターンを取りにいけるような意味のある投資を行うためにもCVCの組織力を高めるべきであり、きちんと出資先企業にコミットできる社員を育成したほうが良いでしょう」
最後は、大企業のCVCに対するアドバイスとして次のように締めくくっていただきました。
中垣氏「最後になりますが、CVCをやること自体が目的ではありません。あくまでも『うちの会社はここを目指すべきだよね』という未来像があり、それを実現するためにオープンイノベーションがあります。そして、オープンイノベーションを推進していく機能としてCVCがあるのです。これを念頭に置いたうえで、取り組みを進めていただけるといいのではないでしょうか」
アメリカと日本における不動産テックの現在地とは?
続いてご紹介するセッションは、「不動産テックスタートアップの現在地」。Metaprop ディレクターの村上 知旨氏にご登壇いただきました。
まず、村上氏はアメリカ市場のトレンドについて、次のように話します。

村上氏「アメリカはファンダメンタルズが力強く、実質GDPも伸びてきています。また、景気後退懸念が薄まり、ビッグ・テックをはじめとするテック企業の株価が持続的に上昇しています。一方で不動産業界においては、金利の高止まりによる資金調達コストの増加で、不動産取引件数が減少しています。そうした状況のなか、不動産テックのなかでも仲介・売買サイトなどのトランザクション・モデルではなく、サブスクリプション・モデルのSaaS企業が優位になっています」
そんな海外の不動産テック市場では、とくにニッチな分野が盛り上がりを見せていると言います。
村上氏「『Matterport(マーターポート)』などのプラットフォーマーが台頭してきたなか、コロナ後で何が変わったかというと、とりわけ不動産業界における業務効率化などでAIを活用する、ニッチ分野で新しいビジネスを展開する企業が増えてきました。不動産のすごいところは、アセットそのものにパワーがあることです。そこに、さらに金融の力で掛け算して大きくしていく、REITや不動産クラウドファンディングなどの分野も成長しています」
続いて話題は日本市場へ。海外とのギャップを踏まえ、次のように話します。
村上氏「日米の違いでいうと、アメリカは合衆国であるためにローカルなディベロッパーが多いんです。そのため、日本でいう三井不動産のような会社が全国をカバーすることはなく、ベンチャーが入っていきやすい環境にあると言えます。とはいえ日本でも、アメリカのようにAIを活用したニッチな分野からスタートアップはどんどん生まれてくると思います。また、海外の投資家から見ると、日本のアセットを買いたいというニーズはあります。そのため、すでにあるアセットを利用したスタートアップも増えていくのではないでしょうか」
最後の話題は「スマートビル」について。日本でもどういう働き方をしたいのかが明確になってくると、スマートビル化も進むと言います。
村上氏「現在は、コロナでオフィス出社という常識が破壊され、いまだ働き方を模索している最中です。スマートビル化はあくまでも手段。そのため『こういう働き方をできたら良いね』が見えてくると、それを実現する手段としてスマートビル化も進んでいくのだと思います」
ソーシャルコワーキングとは?スタートアップにおけるコミュニティの価値
31VENTURESは「THE E.A.S.T. 」という起業家のためのワークスペースも提供しています。ここには、三井不動産と一緒に事業を創っていきたいと考えるスタートアップも入居。その入居企業の1社である株式会社ATOMicaの代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生氏にご登壇いただき、『ATOMicaが目指すソーシャルコワーキングから考えるスタートアップの成長環境』というセッションも行いました。
ATOMicaは「頼り頼られる関係性を増やす」をミッションに、人と人を結び続けることで社会課題を解決するスタートアップです。多様な地域の方々に最適な人を結ぶため、あらゆる願いごと・相談ごと・悩みごとを集め続ける独自の仕組み、「ソーシャルコワーキング®」事業を全国60の地域で展開しています。
そんなソーシャルコワーキング®について、一般的なコワーキングスペースとの違いを嶋田氏は次のように話します。

嶋田氏「ATOMicaが考えるソーシャルコワーキング®とは『多種多様な地域の人々』と『地域のあらゆる願い/相談/悩み』を集め、繋げるための仕組みです。既存のコワーキングスペースだと、『特定の人のみが出入りする場所として、多様性に欠けてしまっているところも多い』『ただ場所に人が滞留しているだけで、出会いやモノゴトが生まれにくくなっている』という課題があります。その解決のため、単なる場所の提供で終わらない、出会いや共創を生むための仕組みがソーシャルコワーキング®です」
ATOMicaが入居する「THE E.A.S.T.」も、単なるオフィススペースとしての機能だけでなく、入居者同士をつなぐコミュニティの機能があります。スタートアップにおいて、こうしたコミュニティの価値を、どう感じているのでしょうか。
嶋田氏「本当に必要なコミュニケーションは、イベントに参加するのではなく、普段の何気ない会話やご飯に行ったときなどの『裏』で行われていると思います。その点、本当に必要なコミュニケーションを生むきっかけを、コミュニティがつくってくれていると思います。また、同じ入居者という共通点でほかの起業家の方とつながりを持つことができる。そうしたつながりから先輩起業家の話を聞くことで、事業のヒントを得るうえでも役立っています」
※31VENTURES Global Innovation Fund 2号を通じて2024年4月に出資
リアルな場でサービスを紹介することの価値を実感。パネル展示を行なった2社の声
最後に、今回パネル展示にご協力いただいた、2社の出資先企業の声もご紹介します。
1社目は、こだわりのスペシャルティコーヒーをアプリから注文、ロッカーから非接触で受け取れる無人のスマートコーヒースタンド「root C(ルートシー)」を展開する、株式会社New Innovationsです。同社のroot C 事業部 ビジネスデベロップメントグループ グループ長の岡澤 友広氏は、今回の展示について次のように反響を話します。

岡澤氏「これまで実際にこういったリアルな場で展示する機会はなかったのですが、日本だけでなく海外の方も来るなかで、多数の商談につながるといった大きな反響がありました。2日間で出会った方々にコンタクトするだけでも充分な結果が得られそうで、リアルな場で実際に人と対話しながらサービスを紹介することの価値を改めて感じました。当社のスマートコーヒースタンド『root C』はオフィスビルと親和性が高いため、今後は三井不動産のアセットも活用させてもらいながら、連携できると嬉しいです」
また、同社は本出展を通じて、来場者が注目の出展スタートアップを表彰する『SusHi Tech Award』において「Fantastic Startup賞」を受賞しました。
※31VENTURES Global Innovation Fund 2号を通じて2023年4月に出資
2社目は、スマートフォンやPC、VR機器など、さまざまな環境からバーチャル空間に集って遊べるメタバースプラットフォーム「cluster(クラスター)」を展開するクラスター株式会社。同社のエンタープライズ事業部 ディレクターの岡﨑 克也氏は今回の展示によって、これまでメタバースに触れたことのない人と接点を持てたと言います。

「今回の展示では、すでに事業をやっている方はもちろん、スタートアップに興味がある方や学生にも来てもらえました。特に若い世代と接点を持てたのは、今回のイベントの醍醐味だと感じています。メタバースにあまり触れたことのない方も多く、実際に手にとって触れてもらったことでメタバースの価値を感じていただける機会になりました。このように、三井不動産と連携することで今までアプローチできていなかったお客様にも、メタバースの価値を提供できたらと思います」
※31VENTURES Global Innovation Fund 1号を通じて2020年1月に出資
二回に渡ってお届けした「SusHi Tech Tokyo 2024」。ベンチャー共創事業部では引き続き多様なパートナーと協業しながら、日本におけるスタートアップエコシステムの創出に貢献していきます。
※出展の裏側や今後の展望を掲載した第一回記事はコチラ